第12回特別展 The Mineral World 人と鉱物のつむぐ物語
- その他
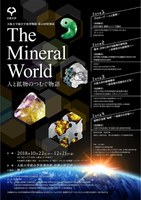
人類は“石”を活用することで文明を発展させてきたといっても過言ではありません。 石器や石材として石そのものを活用した時代から始まり、鉱物から金属を取り出して利用することで、 青銅器、鉄器と扱える金属の数を増やすごとに文明はレベルを上げ、現代の高度なテクノロジーを得るまでに至りました。 また、人類は古来、石に“ふしぎ”な力や性質も見出し、原始には祭礼の対象として祀られました。 “石”のふしぎに魅せられ、探求することで文化的または科学的な発展へと繋がります。 本展覧会では、そんな石の“ふしぎ”に魅せられてきた人類の歴史と発展を東西の石の研究史から紐解きます。 また、石に関わった人々にもスポットをあてます。日本を含むアジア地域では、石の研究は“本草学”という学問領域に含まれていました。日本において本草学は江戸時代に博物学の芽生えともいえる変革期を迎えます。 本草学において石の研究で特に活躍した平賀源内に代表される本草学者たちを本展覧会では紹介します。 しかし、明治維新と共に西洋鉱物学が導入され、研究も変容し、本草学という分野は忘れ去られてしまいました。 ですが日本の近代鉱物学の中において、今でも形を変えて、それらは息づいているのです。 明治維新から現代にいたる、鉱物学者たちの系譜を紐解きながら、その全貌を明らかにしていきます。 エピローグとして、現代そして未来の鉱物学を紹介します。最先端の鉱物研究と活用、そして日本が世界に先駆けて成功した惑星探査“はやぶさ”における宇宙鉱物学の成果を展示します。
| カテゴリ | その他 |
|---|---|
| 日時 |
2018年10月22日(月)から2018年12月21日(金) |
| 会場 | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 |
| 主催 | 大阪大学共創機構社学共創本部/総合学術博物館 |
| 後援等 | 産経新聞社 |
| 問い合わせ先 |
大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 https://www.museum.osaka-u.ac.jp/2018-09-27-12602/ |
◇会 期 平成30年10月22日(月)~12月21日(金)
日曜・祝日休館 ただし11月3日(土・祝)、4日(日)は開館(10:00~17:00)
◇開館時間 10:30~17:00(入場は16:30まで)
◇入場料 無料
◇展示構成
《Zone1 プロローグ~人と鉱物~》
◎日本の国石”翡翠(ヒスイ)”の展示
・人類の文明の発展は”石”の活用と共にある
・”石”について
・鉱物の研究史
《Zone2 東洋、日本における鉱物の研究史~本薬学から鉱物学へ~》
◎江戸期に石見銀山で採掘された銀鉱石(関西初公開)、平賀源内作の火浣布
・本草学
・日本における本草学(江戸期)
・前明治時代の日本の鉱業資源の活用
《Zone3 大阪大学の鉱物標本~研究者の足跡をたどる~》
◎大阪大学総合学術博物館の鉱物標本展示(大阪高等学校旧蔵標本、竹林コレクションなど)
・大阪大学が所蔵する鉱物標本について
・大阪の大地から産する鉱物
・大阪大学にゆかりのある研究者が発見した新鉱物ならびに研究者に献名された新鉱物
《Zone4 鉱物の宝庫”地球”~地球から宇宙へ~》
◎火星や月を起源とする隕石(国立極地研究所蔵)
・鉱物の宝庫 地球の姿
・地球と人類の未来 限りある資源としての鉱物の利用
◇展覧会関連イベント
【ミュージアムレクチャー】
会場:大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館3Fセミナー室
定員:各回30名(申込不要 先着順) 参加費:無料
時間:14:00~15:30(13:30開場)
■11月3日(土・祝) 「”石”と人との物語-鉱物の活用と人類の発展-」
講師:石橋 隆(公益財団法人 益富地学会館 研究員/大阪大学総合学術博物館 博物館研究員
■11月4日(日)「石を見つけよう!!-鉱物ハンティングの楽しみ-」
講師:藤浦 淳(鉱物ハンター/産経新聞大阪本社編集企画室企画担当部長)
■11月17日(土)「鉱物コレクションと展示-日本、欧米、中国の博物館を例として-」
講師:豊 遙秋(元産業技術総合研究所 地質標本館館長/地球科学者/理学博士)
■12月15日(土)「美術にみる石-素材以上に魅力を放つ存在感と力-」
講師:横谷 賢一郎(大津市歴史博物館 学芸員)

