大阪大学総合学術博物館 第7回特別展 「漢方今昔物語: 生薬国産化のキーテクノロジー」
- 科学・技術
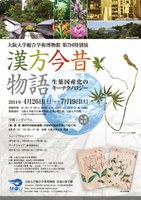
大阪大学総合学術博物館は、第7 回特別展「漢方今昔物語 生薬国産化のキーテクノロジー」を開催します。本展覧会では、江戸幕府の薬草政策の一端を担った史跡・森野旧薬園の温故知新の示唆から22 世紀の薬草政策につなぐ最新の薬・理・農学による共創的連携研究を紹介します。
| カテゴリ | 科学・技術 |
|---|---|
| 日時 |
2014年4月26日(土)から2014年7月19日(土) |
| 会場 | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 |
| 主催 | 主催/大阪大学総合学術博物館 |
| 後援等 | 共催:森野旧薬園、高知県立牧野植物園 協力:農研機構 九州沖縄農業研究センター、(株) 栃本天海堂、小太郎漢方製薬 (株)、奈良県、 パナソニック(株)、大阪大学大学院薬学研究科、兵庫県立人と自然の博物館、大阪大学21世紀懐徳堂、 大阪大学適塾記念センター |
| 問い合わせ先 |
大阪大学総合学術博物館 http://www.museum.osaka-u.ac.jp |
本展覧会では、薬食同源を謳い、自然環境保全や生薬の安全・有効性を担保できる品質に関する国際連携を強め、生薬を国内で確保・供給できるシステムの実用化を目指す研究を発信します。
会期中、 260 年間、門外不出の森野藤助賽郭真写「松山本草」の全カラー映像の初公開や日本の植物分類学の父・牧野富太郎博士の貴重標本資料の展示を行います。
また、関連イベントとして、 学術シンポジウム「医・薬・理・農学の共創的連携:22 世紀の薬草政策につなぐ今」 、 ミュージアムレクチャー (3 回)、 ワークショップ (3 回)を実施します。
開催期間:2014年4月26日(土)~7月19日(土)
休館日: 日曜・祝日 *ただし4月27日(日)、5月3日(土・祝)は開館
開館時間:10時30分~17時 (入館16:30まで)
入館料: 無料
*大学会館は平日のみ開館
ちらしのダウンロードは こちら から
詳細は 大阪大学総合学術博物館HP をご覧ください
【展示会構成】
第1章 温故知新:森野旧薬園と江戸・享保期の薬種国産化
第1部 享保期に発展した本草学の特質
第2部 森野藤助賽郭と松山本草の世界
第2章 生薬栽培の伝統:博物学/植物学から学ぶ生物多様性の原点と実践
第1部 薬草のタイムカプセル:国産生薬のルーツ
第2部 博物館/植物園の機能
第3章 22世紀の薬草政策:文理融合研究が創る実践力
第1部 アクションリサーチ:漢方産業を知る
第2部 マテリアルサイエンス:臨床生薬学
第3部 資源植物学:植物の恵みを資源に変えて
終章 日本の植物研究~本草から植物学へ
【概要
】
|
史跡・森野旧薬園(奈良県宇陀市)は、現存する日本最古の私立植物園で、享保14 年(1729)に森野家10 代目初代藤助通貞賽郭により創始されました。賽郭は漢薬種の育種・栽培・生産など、享保改革期・八代将軍徳川吉宗が展開した幕府薬草政策の一端を担い、本 草学の研鑽を積みながら、栽培者の観察力で薬園内の植物を写生・記録した手稿真写の彩色植物図譜『松山本草(10 巻)』を完成させます。歴代森野家当主と薬園の栽培管理者らの努力は、二次的自然環境を再現する形式(半栽培/半自然)を維持しつつ今に継承されていま す。日本の植物分類学の父・牧野富太郎博士も数度、森野旧薬園に足を運び、異地植物の導入帰化を確認しています。賽郭から始まる薬種国産化の意思は、伝統 殖産として確立された暗黙知と江戸期の大和大宇陀の自然を再現した国内における植物の生息域保全として温故知新の示唆に富みます。 |
【関連イベント】
学術シンポジウム
「医・薬・理・農学の共創的連携:22世紀の薬草政策につなぐ今」
漢方薬原料である生薬の基源種はその大半を野生植物に依存しているため、自然破壊の加速による急速な植物種の消失により維持と安定供給が危惧されている。市場のグローバル化の下、資源小国・日本は使用生薬の絶対量不足が自明で、漢方薬産業は終焉に達する危険を孕む。薬用植物の 栽培化は不可欠 であるが、常法では育種が困難な植物も多く、そのため代替品開発に関して広い視点が必要となる。収益性と生態的持続性を満足する資源植物栽培には、これまでの薬用植物の近縁種と代替種の探索に加え、 新品種薬種栽培型 開発に活用できる 潜在的資源植物の多様化 を意図せねばならない。従来の薬学、理学、農学による相互接点が欠落した非現実的な縦割り研究から脱却した共創的連携こそが、国産薬種殖産の鍵となる。自然環境保全や生薬の安全性・有効性を担保できる品質の標準化に関する国際連携を強め、生薬を国内で確保・供給できるシステムの実用化を目指す研究を発信する。
【日時】2014年6月7日(土) 13:00~17:30
【会場】大阪大学会館 講堂(〒560-0043 豊中市待兼山町1-13)
【参加方法】当日先着順(参加無料、30分前より受付開始)
【シンポジスト】
・高知県立牧野植物園 名誉園長 小山 鐵夫(理学)
・国立医薬品食品衛生研究所 薬学部 部長 合田 幸広(薬学)
・奈良県立医科大学大和医学薬学センター 特任教授 三谷 和男(医学)
・農研機構 九州沖縄農業研究センター 主任研究員 後藤 一寿(農学)
・(株) 栃本天海堂 副社長 姜 東孝(薬学)
・大阪大学総合学術博物館 准教授 高橋 京子(薬学)
ミュージアムレクチャー
高橋 京子(大阪大学総合学術博物館)
田中 伸幸(高知県立牧野植物園)
辻元 康人(奈良県医療政策部薬務課)
※いずれも午後2時~3時30分、待兼山修学館3階セミナー室、定員60名、 当日先着順 (聴講無料、30分前より開場)。
ワークショップ
「450年の伝統を今に伝える~吉野本葛」 株式会社森野吉野葛本舗
「漢方をよりよく、より多くの人に」 小太郎漢方製薬株式会社
「生薬に一意専心~五感でみる生薬の品質」 株式会社栃本天海堂
※いずれも午後2時~3時30分、待兼山修学館3階セミナー室、定員30名、参加費無料、 要事前申込 。
【申込方法】
(ただし、ご家族での応募に限り複数名での応募が可能です。全員分の氏名・年齢をご記載ください)
後日、当否の結果をはがきでお知らせいたします。
申込先:〒560-0043 豊中市待兼山町1-13(大阪大学会館4階) 大阪大学総合学術博物館

