“漆”(JAPAN)の再発見-日本の近代化学の芽生え-
- 文化・芸術
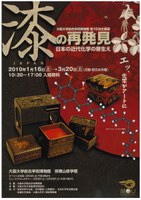
大阪大学総合学術博物館第10回企画展では、しなやかでいて、強く美しい”漆について、その分子構造を解明した化学者・眞島利行(大阪大学理学部化学科の創設者の一人)らの業績をたどり、分かりやすく《漆》について解き明かしていきます。実用性から美の世界までを可能とする「ウルシオール」─それはいかなる物質か? この疑問を探る知的好奇心の旅へと皆様を導きます。入場無料です。
| カテゴリ | 文化・芸術 |
|---|---|
| 日時 |
2010年1月16日(土)から2010年3月30日(火) |
| 会場 | 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 |
| 主催 | 大阪大学総合学術博物館 |
| 後援等 | 大阪大学大学院理学研究科 |
| 問い合わせ先 |
大阪大学総合学術博物館 TEL:06-6850-6715 http://www.museum.osaka-u.ac.jp/jp/event_content/encaenia-2009b/index.html |
私たちは《漆》を用いた道具や装飾品に囲まれて生活しています。かつて欧米で“japan”(ジャパン)が「漆器」の意味でも用いられた
ように、ウルシノキなどの樹液を用いた天然樹脂塗料である《漆》は日本人と密着し、古くから様々な用途に用いられてきました。
何度も塗り重ねら
れた《漆》は、固まると丈夫な表層を形成してモノを保護します。仏像の造像、武将の甲冑にも使用されました。さらに黒や朱色の光沢の美しさと螺鈿(らで
ん)、蒔絵(まきえ)、堆朱(ついしゅ)などの加飾技法は、美しい工芸品を生み出し、桃山時代の高台寺蒔絵など息をのむ美しさです。
■ 会期:
2010年1月16(土)~3月30(火) 好評につき期間延長!
■ 会
場:
大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館
560-0043大阪府豊中市待兼山町1-20 TEL:
■
開
館時間:10時30分~17時
■入場無料
■ 出品内容(予定)
眞島利行関係資料(実験台、高度減圧蒸留装置、常圧還元装置、オゾン分解装置
ほか)
実物・模型による漆製品・代替品など 眞島利行の門下生による天然物化学の発展資料
阪大理化における最新研究の成果を紹
介(映像) 漆による美術工芸品等
旧そごう心斎橋店のエレベーター扉(島野三秋作、漆塗・螺鈿細工、昭和10年) 天平時代仏像・乾漆像
模造試作品(乾漆像、日本美術院国宝修理所) 漆工芸品(中国の前漢時代から清時代の工芸品、日本の桃山時代、江戸時代の作品から現代 の人間国宝北
村昭斎氏作品など)

